
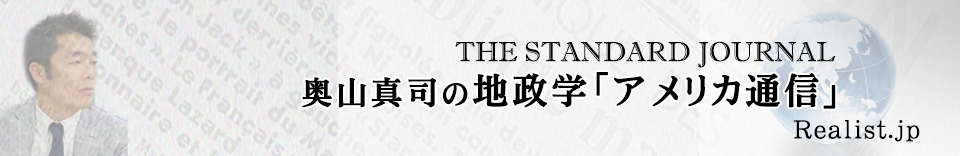

ではそもそもなぜこのようなことが起こるのでしょうか?
もちろん多くの歴史家たちは
似たような循環が起こっていることを指摘してきたわけですが、
なぜこのような循環が起こるのか、その原因までをくわしく説明した点で、
本書は画期的なのかもしれません。
その理由は、ハウとストラウスによれば、
人間の人生の四段階に関係しているといいます。そしてその四段階とは、
幼年期→成人期→中年期→老年期
というものであり、それぞれの段階が、
やはりおよそ20年ごとに区切られている、というわけです。
このような人間の人生のステージの移り変わりというのは、
もちろん古代からすでに様々な文献の中で触れられておりますし、
普通に人間観察をしていれば、
当然の帰結として出てくる分析といえるでしょう。
人間がオギャーと生まれ、戸惑いながらも成人し、
社会的に責任を負うようになって、最後に死を迎える、というのは、
どの時代・どの文化にも普遍的に当てはまるものだからです。
ところがこの四段階は、そのまま自然の中の
季節のめぐりあわせにも対応するのでは?
というのがハウとストラウスの目の付け所。
つまり人間の人生のステージは、
自然の中の季節と対応するようにできており、
幼年期→成人期→中年期→老年期という移り変わりが、そのまま
春→夏→秋→冬
という一年の中での「四季」になるというのです。
われわれ個人の人生の中には、
幼年期→成人期→中年期→老年期という春夏秋冬はあるわけですが、
たとえばこれを書いている私は、「世代」としては「遊牧民」に属しており、
人生の春夏秋冬を経験しつつも、生まれてから死んでいくまで
「遊牧民」というくくりから抜け出すことができません。
あなたの世代がどのようなものであれ、
その世代も必ず「春夏秋冬」という四つのステージを、
その世代なりの特徴のある形で経験していく、ということなのです。
ところがここで最大の問題が出てきます。
「世代も四タイプあり、自然には一年の間に四季があり、
そして人生にも四季がある」というのはわかったとして、
ではそもそもこの「世代」の特徴を決定づけるものは一体何なのか、
そもそもなぜ「世代」はこんなに違うのか、
という疑問が出てくるからです。
その答えとして、原著者のハウとストラウスは、
ここでも「四季」を指摘します。つまり、時の流れにも四季がある、
というのです。
確認します。ここまで、世代、自然、そして人生にも、
すべて4タイプあることを説明してきました。
ここにハウとストラウスは時代(社会の雰囲気)にも
4タイプの四季があるとして、以下のような分類をしております。
春の時代:第一の節目・高揚(High)
夏の時代:第二の節目・覚醒(Awakening)
秋の時代:第三の節目・分解(Unraveling)
冬の時代:第四の節目・危機(Crisis)

上昇的な時代だとされます。新しい社会秩序が浸透して、
古い価値による制度が崩壊していくことになります。
次の夏の時代ですが、これは精神面での激変が起こる情熱的な時代です。
既存の社会秩序が、新しい価値観による制度から挑戦を受けるようになり、
ちょっとした社会的動乱が避けられない時代です。
ピークを過ぎて秋の時代になると、個人主義が強化されて、
社会制度などが弱まる下降的な時代であるとされます。
それまでの社会秩序は衰退して、
新しい価値観による制度が植え付けられはじめます。
最後の冬の時代には、社会が激動を迎え、
それまでの古い価値観が新しいものととって代わり、
社会秩序の変化が決定的に進められることになります。
「なるほど、時代にも春夏秋冬があることがわかったとして、
これは最近のどの時代に当てはまるの?というか、今はどの時代なの?」
という方もいらっしゃるでしょうから、
以下に直近の春夏秋冬の時代区分を挙げておきます。
ハウとストラウスによれば、
春:1946-1964年
夏:1964-1984年
秋:1984-2004年
冬:2005-2025年
となり、現在は冬の時代のちょうど真ん中あたり(!)ということになるわけです。
そしてここでも重要なのが、時代も約20年ごとに区切られている、
ということなのです。20年というのが重要だというのです。
- ※ - - ※ - - ※ - - ※ - - ※ - - ※ -
▼ 奥山真司による『The Fourth Turning』解説(その1)
▼ 奥山真司による『The Fourth Turning』解説(その2)
▼ 奥山真司による『The Fourth Turning』解説(その3)
▼ 奥山真司による『The Fourth Turning』解説(その4)
- ※ - - ※ - - ※ - - ※ - - ※ - - ※ -