訳者:奥山真司による本書の解説
この「なぜリーダーはウソをつくのか」のエッセンスを一言でいえば、
「国家のリーダー同士は互いにそれほどウソをつかないが、
国民に向けてはウソを頻繁に使う」という意外な結論にある。
まさかこのような結論に至るとは、
原著者であるミアシャイマー教授自身も
「最初は信じられなかった」
と書いているが、たしかに歴史を紐解いてみると、
国家間のやりとりにおいて明らかな「ウソ」が使われた事例は
あまり認められない、という説明には説得力がある。
つまり本書の意義は、原著者であるミアシャイマー教授の意図する通り、
「摩訶不思議で厳しい国際政治の新しい面を知る」ということにある。
そして、本書の優れている点はそれだけではない。
この本には、これまでに私が訳してきた幾つかの書籍と同様に、
私たち個人にとって非常に多くの「発想のヒント」や
興味深い示唆を与えてくれるのである。
▼現実世界では、この本は具体的にどう役に立つのか?
我が国では「ウソはついてはいけない、正直に生きよう」という、
素晴らしい文化的伝統が現在まで脈々と受け継がれているが、
異文化との衝突、異民族との間の殺戮合戦をくり返して、
否応無しに身も心も鍛えられてきた諸外国の人々にとっては、
「ウソをうまく使うことは、ある意味、当然である」
という認識・意識が厳然と存在していることは否めない。
ところがグローバル化した現在の世界情勢下においては、
諸外国と外交を行う際に、相手の繰り出してくる「ウソ」や「騙し」に対して、
日本人だけが極めて鈍感であり、国際社会の冷酷な現実を知らない、
というのがいかに致命的で「ナイーブ」なものであるかは容易にご理解いただけよう。
我々日本人が普段ほとんど行うことのない知的作業、
すなわち「ウソ」そのものを「分類」する、
という極めて特殊なことを行っていることに、この本の意義がある。
ミアシャイマー教授は今回の著書の中で、「ウソ」だけでも
1)「戦略的」
2)「自己中心的」
なものの二種類があること、そしてさらに、「騙し」の仲間として、
1)「印象操作」
2)「秘匿」
という二種類を挙げて、詳細な分類を行なっている。
必ずしも論理的思考に慣れているわけではない我々日本人からすると、
「そのような"理屈っぽい"知識など何の役に立つのだ!」
と、思ってしまいがちである。
しかし、今後、グローバル化が増々進む世界において、
日本人が外国人と交渉・折衝を行う際には、
このような知識はデフォルトとして認識しておくべきものなのだ。
そして本書からはそのような普通のビジネス本には書かれていない、
基本的な認識・知識を大いに学ぶことができるのである。
たとえば「印象操作」に類するものは、
実際に日本でも、就職活動などをはじめ、
ビジネスの現場においてはごく日常的に行われている、
ということは、いかに「ナイーブ」な我々でも、
リアルに実感出来るのではないだろうか。
そして、外国の友人やビジネスパートナーがいる方であれば、
ある程度は実感していると思うが、
彼らは「ウソ」そのものはあまり言わない代わりに、
「印象操作」や「秘匿」を駆使した、
「騙し」を日常的に行っていることが理解できるのだ。
-*- -*- -*-
本書はそれ以外にも、日本国内はもちろん、
海外のメディアの情報を分析する際などに、
彼らのいわゆる「レトリック」などを見抜くのに
活用することができる。
たとえば、ある一つの情報が報じられた際に注目すべきは、
その情報が「何を報じたのか?」
ということよりも、
「何が報じられなかったのか?」
という点にあることは、情報分析の初歩の初歩である。
つまり、この「知らされなかった部分」を本書の内容に即して言えば、
「戦略的隠蔽」や「秘匿」になるのだが、
これを知るために伝統的に使われてきた手法が、
いわゆる「スパイ」であり、
それに関する活動などを学問的に研究しようということで
最近注目されているのが「インテリジェンス」という分野である。
更に、このスキームを「個人」の分析に適用してみることも可能だ。
まさか本書のアイディアが個人に使えるはずがない、
と思われるかもしれないが、
発想豊かに拡げ、分析の対象・範囲を拡大して解釈してみると、
例えば、
「自分の正直な気持ちにはウソをつきつつ、他人には素直な気持ちを話している」
といった行動を取る人がいることにも、なるほど、納得出来るのである。
つまり自分を客観的に分析する際にも、
このミアシャイマー教授のスキームは多いに活用出来るわけである。
-*- -*- -*-
本書を実際に手にとって読み始めて頂けば
直ぐお気付きになると思うが、
ミアシャイマー教授のその他の著書と同様、
各章毎の構成がスッキリとした論理構造になっているので、
その構造の大枠さえ先に掴んでしまえば、
自らが興味を惹かれた章から読み進めるのも良いかもしれない。
それよりも重要なのは、
これから先、我が日本国が対峙せざる得ない、
諸外国との厳しい交渉・折衝の場において
確実にサバイバルするため「嗅覚」を
本書お読みになったみなさんも身に付けて頂きたい、ということだ。
それこそが「リアリズム」学派における世界的な泰斗である
ミアシャイマー教授の著書を皆さんに紹介している、本当の狙いでもあるのだ。
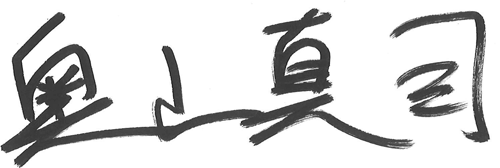
- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
●ジョン・J・ミアシャイマーの経歴●
ミアシャイマーは一九四七年にアメリカのニューヨーク市に生まれ育ち、
ベトナム戦争が激しくなっていた時期に一七歳から米陸軍士官学校として名高い
ウェストポイントに入学し、卒業している。
その後の五年間は空軍に勤務しながら南カリフォルニア大学で一九七四年に
国際関係論で修士号を修了し、そのままコーネル大学に入学して
抑止理論などをテーマにして、ジョージ・クエスター(George H. Quester)や
リーチャード・ローゼクランス(Richard N. Rosecrance)などの指導の下で
一九八一年に博士号を取得している。
在学中からリベラル寄りとされるブルッキングス研究所で研究員をつとめており、
卒業後はハーヴァード大学の研究所で二年ほど研究員も務めてたあとに
シカゴ大学へ移り、以来そこでシカゴ大学一筋で教え続けている。
コーネル時代に書いた博士号論文は一九八三年に『通常兵器による抑止』
(Conventional Deterrence)という題名の本としてまとめられて出版され、
当時の英語圏の安全保障業界に衝撃を与えている。
これは後の『大国政治の悲劇』と共に、学術賞を受賞している。
保守派的・タカ派的な理論のおかげでアメリカの共和党寄りな
政治思想を持っているのかと思いきや、実は民主党に人脈があるようで、
一九九二年には当時のクリントン政権に国防長官として採用される
という噂も出たことがある。
また、アメリカの外交政策に大きな影響力を与え、
豊富な資金源もあるシンクタンクである「外交問題評議会」
(the Council on Foreign Relations: CFR)とも関係が深く、
一九九〇年代後半には前述した主著である『大国政治の悲劇』
を書くためにここの特別研究員を務めたほか、
現在もこのメンバーとして名を連ねている。
専門は安全保障を中心とした国際関係であり、国際政治の動きを
主に安全保障の観点から予測・分析する、
正真正銘の「現実主義者」(リアリスト)と呼ばれる理論家である。
とくに彼は国際社会をシステム的に構造分析することを得意とすることから、
リアリストの中でも「ネオリアリスト」(新現実主義者)に分類されている。
厖大な数の論文の割には著作の数は少なめで、博士号論文が元になった
デビュー作である前述の『通常兵器による抑止』の次に、
イギリスの有名な歴史家・ジャーナリストであるバジル・リデルハート
(Sir Basil H. Liddll-Hart)を痛烈に批判した
『リデルハートと歴史の重み』(Liddell Hart and the Weight of History)
を一九八八年に出版している。以降は主に議論の的となった
有名な論文をいくつか発表しており、たとえば冷戦直後の一九九〇年夏に、
世界(とくにヨーロッパ)の多極化をリアリズムの理論から予言した
「バック・トゥー・ザ・フューチャー:冷戦後のヨーロッパの不安定性」
(Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War)
という題名の論文を、高級専門誌であるインターナショナル・セキュリティー
(International Security)誌に掲載して大きな話題になり、
一九九四年末には 国連のような国際制度機関は大国の行動には
影響を与えられないという挑発的な内容の「国際制度機関の口約束」
(The False Promise of International Institutions)という論文を書いて、
これも議論を巻き起こしている。
そしてこのような論文の中で示したアイディアの集大成として、
二〇〇一年に満を持して『大国政治の悲劇』(Tragedy of Great Power Politics)
という理論書を出版し、これも学術賞を獲得している。
九〇年代からアメリカの介入過剰で節度のない外交政策には
不満を抱いていたようであり、
二〇〇三年のイラク侵攻の前後から「ネオコン」と呼ばれる
ユダヤ系知識人を中心とするアメリカの中の親イスラエルのタカ派の人々を
痛烈に批判する論説記事を書いたり、彼らと公開の場で議論を行ったりしていた。
ところが実際にイラク侵攻が行われるとミアシャイマーはとうとうしびれを切らし、
二〇〇五年にはシカゴ大学の元同僚のスティーブン・ウォルト(ハーヴァード大学教授)と
共著の形で「ロンドン・レビュー・オブ・ブックス」に論文を書き、
それを後に本にまとめたのが『イスラエル・ロビーとアメリカの外交政策』である。
これはイスラエルにあまりに肩入れをするロビー団体が
アメリカの外交政策を誤った方向に導いていると大批判をして国際的に話題になり、
二一の言語に翻訳されたほかにも、世界各地に出版記念講演ツアーに出向いている。
他にも『大国政治の悲劇』の最後の部分で展開された、
「中国が東アジアの覇権を目指すのは確実だ」とする、
いわゆる「中国脅威論」を展開しており、フォーリン・ポリシー誌上で
「中国を取り込んでしまえば怖くはない」と主張する
カーター大統領の元外交アドバイザーで、アメリカの外交政策の重鎮として有名な
ズビグネフ・ブレジンスキー(Zbigniew Brzeziński)と論戦を行い、
「危険な国際政治では国家は可愛いバンビちゃんになるよりゴジラになったほうがいいのだ!」
と論じて真っ向勝負を挑んでいる。
- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
■本書の特徴■
本書は基本的に国際関係で、とくに国家のリーダーの間で使われるウソを分類した、いわば入門書的な体裁で書かれているが、国際的な外交史の雑学書的な性格をもつと同時に、とくにブッシュ(息子)政権におけるアメリカの大戦略や、イスラエルの対パレスチナ政策への痛烈な批判書という風にも受け取れる。
本書が書かれた出発点はニューヨークタイムズマガジン(ニューヨークタイムズの日曜版についてくる雑誌)の編集者であるサージ・シュメマン氏に一本の電話をもらったことであった。この時の会話をメモを基にして何度か講演を行った時に、熱い聴衆の反応を引き起こしたことから、これを基にして論文を書いてまとめたのが本書である。
つまり本書は意外な人物(一度も顔を合わせたことのない人)からの質問という形で始まり、それがイラク戦争におけるブッシュ政権のウソと、イスラエルの国際政治における発言権の大きさという、彼の中の二つの問題意識と化学反応を起こした結果としてできたものであると言える。
まず本書でもっとも際立っているのは、国家のリーダーが使う相手国にたいして使うウソ(「国家間で使われるウソ」)というものを系統立てて考察している点であろう。
もう一度ここでおさらい的に振り返ってみると、まずミアシャイマーはウソというものを体系的に考えるために、まずは人間が相手に物事を伝える行為を大きく「真実の供述」(truth telling)と「騙し」(deception)二つに区別しており、それを元に以下のような分類を行っている。
●「真実の供述」(truth telling)
vs
●「騙し」(deception)
1、「ウソをつく」(lying)
1-1「戦略的なウソ」(strategic lies)
「国家間のウソ」(inter-state lies)第三章
「恐怖の煽動」(fearmongering)第四章
「戦略的隠蔽」(strategic cover-ups)第五章
「ナショナリスト的神話作り」
(nationalist mythmaking)第六章
「リベラル的なウソ」(liberal lies)第七章
1-2「自己中心的なウソ」(selfish lies)
「無能の隠蔽」(ignoble cover-ups)
「社会帝国主義」(social imperialism)
2、「秘匿」(concealment)
3、「印象操作」(spinning)
そしてこのような分類から、彼は(1)の「戦略的なウソ」の五つのウソを中心に、それぞれについて代表的なケースを提示しながら、本書で分析を行っていくのだ。
本書の結論は、著者も告白している通りに一般的なイメージとは違って「意外なもの」である。それを一言で言えば、「国家のリーダー同士は互いにあまりウソを使わないが、自国民にたいしてはかなりウソをつく」というものだ。ミアシャイマー自身も「リアリスト」という立場から、当初は国家間でウソが多用されているという想定をしていたらしいが、実際に調べていくとその反対の結果ばかりが出てきたとしており、その結論に自分でも驚いた様子がうかがえて興味深い。
また、彼は意外なところで自分の得意な国際政治の理論と分析をつなげている。たとえば結論の一番最後の部分で、ミアシャイマーはアメリカのリーダーたちが将来において「恐怖の煽動」というウソを使い続けることを予言しており、その理由としてアメリカは、(1)「選択の戦争」を、(2)遠くの場所で行おうとする、(3)民主制国家、という三点を挙げているのだ。
ミアシャイマーは前々著の『大国政治の悲劇』で、「大国は本来攻撃的なものだが、大きな水(海)があると攻撃性は和らぐ」という主張をしており、本書でもその理論の根拠となる「水の制止力」(stopping power of water)という概念を提唱しているのだが、アメリカのような島(北アメリカ大陸は島であると認識されている)にある大国は、ユーラシア大陸の国から侵略される危険がなく十分安全であるために、海外に自国の国益をかけるための戦争をしなくても良いということになる。
ところがアメリカはすでにユーラシア大陸に大きな権益を持っているため、すでに十分安全であるにもかかわらず、余計な武力介入を行なおうという動機をエリートたちが持っており、さらにアメリカは民主制国家であるために、リーダーをはじめとするエリートたちは、海外での武力介入を正当化しようとして自国民にウソ(この場合は「恐怖の煽動」)を多用することになるというのだ。
つまりここではミアシャイマーが本来得意とする「国際政治の枠組み」というフレームワーク(「水の制止力」という地政学的な要因も含むと考えられる)だけではなく、「民主制国家」という国内制度の性格と、「リーダー」という国家を代表する「個人」の役割にフォーカスを当てているのだ。これは「国家というのはビリヤードの玉と同じですべてが材質的には同じであり、違うのはその(パワーの)サイズだけ」という議論を行っていた前々著での説明から大きく離れたと言える。
彼のこのような分析を考える上で参考になるのは、私が他のところで何度も指摘している、ケネス・ウォルツ(Kenneth Waltz)の提唱した、国際政治の動きを見る際の「三つのイメージ」という考え方だ。
ウォルツは一九五九年に、自身がコロンビア大学の博士号論文として書いたものを『人間、国家、そして戦争』(Man, the State, and War)という本にまとめて出版している。この本の内容を簡単にいえば、「政治哲学では、いままで戦争の原因という重大なテーマについて、主に三つのレベルで説明がなされてきた」というものだ。
この「三つのレベル」とは、戦争の原因というものを、第一に個人や人間の本質(human nature)のレベルに求めて説明するもの、第二に政党や官僚組織、もしくは国家のレベル(ユニット・レベルとも言う)から説明するもの、そして第三に国家同士のバランスや国際関係の枠組みのレベル(システム・レベルとも言う)から説明するものに分類している。ウォルツはこれを自分の奥さんの助言によってそれぞれ
(1)「ファースト・イメージ」(First Image)
(2)「セカンド・イメージ」(Second Image)
(3)「サード・イメージ」(Third Image)
と名づけており、結論としては戦争の原因として一番重要なのが(3)「サード・イメージ」の国際的なレベルであると指摘している。そしてこの枠組みを使って、後に「ネオリアリズム」という学派を創設するきっかけとなった『国際政治の理論』(勁草社、二〇一〇年)という本を一九七九年に完成させて出版している。
ウォルツはこの本の中で、純粋に(3)の「サード・イメージ」による説明だけを使いながら、出版当時の冷戦の二極構造を社会科学的に論述して世界の国際政治学界に衝撃を与えたのだが、同じくネオリアリストに分類されるミアシャイマーも「攻撃的リアリズム」という自分の理論を、あえてシステムレベルの(3)の「サード・イメージ」という、国際的な枠組みやバランス・オブ・パワーという概念だけを使って、より大きな視点からの説明を行っているのだ。
そしてその成果が前々著の『大国政治の悲劇』なのだが、面白いことにその後のウォルトとの共著の『イスラエル・ロビー』では、アメリカ国内のロビー団体の影響力を分析したという意味で焦点を「セカンド・イメージ」に主に焦点を当てたものになっている。そして本書では、とうとう国家のリーダーという「個人の使うウソ」を研究したという意味で、「ファースト・イメージ」を分析しているのだ。
ミアシャイマー本人はどこまで意識しているかわからないが、彼は二〇〇〇年代を通じて、その分析を「サード・イメージ」から「ファースト・イメージ」まで下ろして来た、という風に言えなくもない。
( おくやま )

