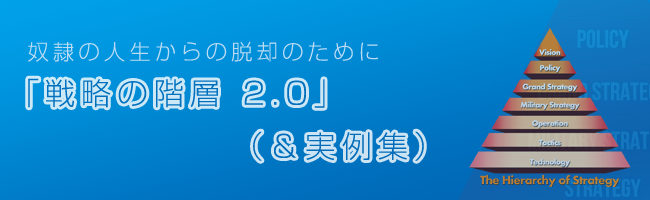今回はタイムリーな話題である「竹島問題」
を取り上げたい気持ちをぐっとこらえて、
前回からの続きとして、尖閣における日中間の戦略を分析するための
具体的な「前提」について考察してみたい。
まずお断りしておきたいのは、私は中国問題の専門家ではない。
それでも、あえて私がこの尖閣問題を取りあげるのはなぜか?
それは、この対立構造に内在する「戦略」のロジックが
文化を越えて世界共通なものであり、
より身近な問題である尖閣諸島をめぐる日中問の問題にも、
それがズバリと当てはまってしまうからだ。
我々日本人は、一般的にものごとを
「そもそも論」から考えるような習慣があまりないので、
原発事故の問題や、国の安全保障問題など、
人命に関わってくるほど深刻なトピックでも、
その初動段階から問題への対処を大きく誤ってしまうことが多い。
尖閣問題もこの例外ではなく、
日本のメディアの分析でも、戦略論のレンズを通してみれば
かなりトンチンカンなものが多いのだ。
私は「アメ通」読者の皆さんには
そのような過ちを犯して頂きたくはないので、
あえて専門外の日中問題の分析を試みている。
-*--*--*-
それでは、尖閣を巡る「前提」を具体的に考えてゆこう。
私は大きく見て六つあると考えている。
---------------------------------------------------
(1)「尖閣を巡る日中間の衝突は必ず起きる」
(2)「中国は米国との直接対決は出来るだけ回避する」
(3)「中国は"抵抗最弱部位"を狙ってくる」
(4)「中国はあくまでも政治的に動く」
(5)「実は現場レベルでは統制が取れていない」
(6)「日中衝突の展開を厳密に予測することは不可能」
---------------------------------------------------
今回の「アメ通」では、まず(1)と(2)について述べてみたい。
まず一つ目の「前提」は、
「発生のタイミングは不明だが、
尖閣における日中衝突はいずれかの時点で必ず発生する」
というものだ。
私が專門とする「戦略学」においては、
まず最悪の事態を想定することから
論を進めてゆくのが基本である。
これは皆さんにもお馴染みのことわざの、
「備えあれば憂いなし」がそれである。
しかし、現在の我が国の体制はどうなのかと言えば、
政府上層部ですら、十分な準備を備えていないのでは...?
と思わざるを得ない状況であり、言うなれば、
「憂いがないから備えもない」
とでもいうような、なんとも情けない状態に見える。
中国問題の専門家の見解を一通りみる限り、
衝突の起こるタイミングについては若干の違いがありつつも、
次の衝突そのものが発生する可能性を否定している分析は、
ほとんどないと言ってよい。
つまり、衝突は必ず起こるという「前提」なのだ。
この「前提」は決して荒唐無稽なものでもなく、
最近増加しつつある中国軍の艦船や航空機の
日本の領海・領空侵犯というリアルな事例をみても
その衝突の可能性は、高まりこそすれ低くなることはなさそうだ。
二〇一〇年九月に起こった、中国漁船と海保の巡視艇の衝突事件以来、
尖閣諸島周辺での中国漁船や公船の侵入は断続的に続いている。
二〇一〇年三月から四月にかけて、
一六隻もの中国海軍の艦船と潜水艦が
沖縄本島と宮古島の間の海域を通過したという報道もあった。
この記事が掲載されたのは、一部で"親中的"とも評される
あの「日経新聞」であるが、中国とはあまり事を荒立てたくない...
という意向をもっている者から見ても、
中国軍の活動は目に余るということなのである。
もちろん、衝突など起きないことが理想だが、
戦略を考える上で、最悪の事態を「想定」することは、
あえて論ずる事を忘れるほど自明のことなのである。
-*--*--*-
二つ目の「前提」は、
「中国はアメリカと直接対峙するつもりはない」
というものだ。
近年、その国力に陰りがみえてきた
とも噂されるアメリカではあるが、
軍事面でのテクノロジーやシステムでは
まだ圧倒的な力を誇っており、
近年劇的に軍事力を増大しつつある中国とはいえ、
これに正面から対抗しようという意図はあまり見られない。
軍事的なバランスという意味では、
依然としてアメリカのほうに大きなアドバンテージがある。
これとは対照的に、日中間の軍事バランスが拮抗してきていることは
各種データからも明らかであるが、
それは実際の中国側の姿勢や態度にも現れている。
例えば今年の七月一一日に、
中国の漁業監視船三隻が尖閣周辺の海域に侵入してきた。
日本の海上保安庁の巡視船は通常は四隻体制で警戒するようだが、
この三隻の中国船団は逆に海保の船に向かって
「中国の領海から離れろ」と言い放ったのだ。
また、中国側があからさまに「格下」と見做している、
フィリピンやベトナムといった国々が相手の場合は
より挑発的な行動に出ている。
つい最近も領有権を争っている中南沙諸島周辺に
新たな行政区として「三沙市」
を設置したことがニュースになったが、
このケースでは、アメリカもあからさまに介入を避けるかのように、
表向きは領土・領海問題では「中立」の立場を崩しておらず、
それをいいことに、中国は「実効支配」している島々に
臆面もなく堂々とレーダーなどの建造物を設置し、
着々と狡猾に「既成事実」を積み上げている。
このような実際の事例からも明らかなように、
直接的な軍事的脅威にはならず、
総合的な国力で比較して取るに足りないと見做した相手には
傍若無人に「実効支配」のための布石を打ってくるのが、
これまでに中国大陸に成立してきた「王朝」の伝統的なやり方である。
ある意味で、「リアリズム」を強烈に信奉しているとも言える中国は、
アメリカのような強大な「覇権国家」とは、
表向き、極力事を荒立てたくはない様子を見せるが、
フィリピンやベトナムのような「格下」と見下した国に対しては、
侮蔑的とも言える強気な態度を取ることは、
読者の皆さんもよくご存知であろう。
では、その現在の中国「王朝」が、
日本政府及びわれわれ日本人をどう観ているのか?
ここで、これ以上私が多くを語る必要はないだろう。
-*--*--*-
さて、これまで紹介した2つの「前提」は、
読者の皆さんにとっても、
比較的分かり易い話だったのではないだろうか。
このような前提と密接に関係してくるのが、
三つ目の「中国は抵抗最弱部位を狙ってくる」というものでる。
あまり聞き慣れない、この「抵抗最弱部位」ということを
説明するには紙面が尽きてしまったので、
次回も引き続きこの話を続けてゆきたいと思う。
(おくやま)
戦略を語れない人生は奴隷だ
技術を制するのは高度な技術ではない。より上流階層からルール決めには対抗できない。
今こそ日本人は「戦略の階層」を学び、その全体像を理解しなければならない。
このサイトはリアリズムについて学ぶ人を増やすためのサイトです。
さて、早速ですが、・ネオコンをはじめとする勢力が狙ってきた米国の世界一極覇権支配は、長くは続かない。・中国が膨張し、アジアの覇権をねらい、世界は多極構造になる。 90年代から上記のように予想し、米国内でも論争してきたのがリアリスト学派です。
リアリスト学派は、国家のパワー(軍事力、政治力、人口規模、経済力等)がもっとも大事な要素と考え、
「正義やイデオロギー、理念は関係ない。国際関係はパワーで決まり、パワーを予測し戦略を立てよう」
と考える学派で、19世紀の英国の行ったバランス・オブ・パワーを活用した大戦略を信条とします。
ところが「リアリスト」を自認する日本の親米保守派は、
「経済中心主義」で「安保無料(だだ)乗り」をし続けていますが、
実は、彼らは、以下の2点で決定的、かつ、致命的な誤りを犯していたのです。
そして、そうした日本の政策は、冷酷な米国のリアリストから、
単なる「バンドワゴニング」に過ぎない、と足元を見透かされているのです。
その2点とは、
(1)日本はアングロサクソン(米英)についていれば大丈夫。
(2)米国は「民主制度」と「法治」、「人権」を重んずる日本を信頼し、
一党独裁の共産主義中国を嫌っている。
ということです。
まず、(1)については、
日英同盟時も上手くいった。だから、これからも米国についてゆけば大丈夫!
万事問題ないというものです。
しかし、我が日本が戦後60年間、幸いにして戦争に巻き込まれなかったのは、
ほとんど偶然の産物であったということは、強く認識しておく必要があります。
米国は国益に係わることならば、いとも簡単に「友達」を切り捨て、裏切る国である。
国論が変われば友好国をあっさり切り捨ててきたことは、これまでの歴史の事実が証明しています。
・日中戦争では、蒋介石を応援しつつも、途中から毛沢東支援にまわった。
・ソ連打倒のためには台湾(中華民国)を切り捨て、中華人民共和国と国交を結んだ。
・ベトナム戦争では出口がみえなくなり、結局南ベトナム支援からあっさり撤退した。
・米国が支援していた南ベトナムは崩壊し、大量の難民があふれ出た。
・イラン・イラク戦争の時、イランが戦争に勝って影響力が拡大することを恐れた米国は、
サダムフセインに(イラク)に軍事的な支援をした。
しかし、支援した米国は干渉してこないと思ったフセインは、その後クウェートに侵攻し、
湾岸戦争、イラク侵攻と2度の戦争で米国に打ちのめされ、最後は米軍に捕まり処刑された。
如何でしょうか?
これでもまだあなたは、アメリカはずっと「友達」でいてくれる!
と思えますか?
次に、(2)についてですが、
欧米メディアなどの報道によれば、米国内における中国の工作員の数は激増しています。
更には、人民解放軍には「政治工作条例」なるものまであります。
彼らは世論戦、心理戦、法律戦からなる「三戦」の任務を与えられ、
まさに今、中国は国策として、米国内で「世論戦」を仕掛けている、というのが冷酷な事実です。
正義や真実でなく、ウソでも現実をつくれると考える中国の
カネも人員もかけたまさに「人海戦術」的な、この国家戦略が功を奏し、
すでに米国世論では「尖閣は日本が強奪した島だ」ということに傾き始めている・・・
この危険な状況を皆さんはご存知でしょうか?
-*- -*-
例えば、韓国との従軍慰安婦問題をみるまでもなく、
日本国内で、いわゆる「保守派」といわれる人達が、
どれだけ「真実」を主張しても、
同じ日本人であるはずの国内左翼勢力がこの外患に呼応するという、
典型的なパターンに陥っている事例は、枚挙に暇がありません。
白州次郎は「日本をプリンシプルのない国」と言いました。
しかし、残念ながら、この分析は現在の日本にも今だに当てはまっているのです。
これらの冷酷な事実を踏まえ、
本サイトで皆さんとともに真剣に考えていきたいのは、以下の2点です。
・日本はいかにして「パワー」を獲得すればいいのか?
・どんな国家像を描き、グランド・ストラテジーを立てればよいのか?
この二つの質問を念頭に据えて、米国のリアリスト思考を学び、
日本におけるリアリスト思考を広げ、リアリスト学派をつくっていく。
これが、このサイト、www.realist.jpの目的です。
あなたも是非議論に加わって下さい。
リアリスト思考を最初に日本にもたらした、
シカゴ学派、元フーバー研究所上席研究員、故・片岡鉄哉先生に捧ぐ
日本がこのままの状態でいけば、
少なくとも十年以内に、二流、三流の地位まで確実に堕ちていくことになる。
現在の日本の状況を冷静に見れば、
どう考えてもそういう結論しか出てこないのだ。
しかし、日本はそのまま堕ちっぱなしというわけではない。
何年後になるかわからないが、日本はしぶとく復活するはずである。
国家というのはいつまでも堕ちっぱなしということはなく、
反省して自覚した国民が生まれ、それが国を復興することになるからである。
そのときに、決定的に必要となつてくるのが「理想」である。
地政学の祖であるマッキンダーは、
「人類を導くことができるのは、ただ理想の持つ魅力だけだ」
と言っている。
しかし彼は、同時に現実を冷静に見る目を
忘れてはならないことを鋭く警告している。
それが地理と歴史を冷静に分析した、
地政学という学問が与えてくれる視点なのである。
彼が一九一九年に発表した『デモクラシーの理想と現実』
という本の題名は、このような理想と現実のバランスの大切さを訴えている。
世界はこれから「カオス化」していく。
これはつまり、世界はこれからますます複雑化した
先の見えない場になるということである。
自立を目指さなければならないし、
むしろ自立せざるを得ない状況に追い込まれることになるかもしれない。
そして、その中で世界に伍していくためには、
日本人は何よりもまず、リアリズムの思考法を身につけなければならない。
日本人は自分で責任を持って戦略を考えるという思考を捨ててしまい、
安易に平和的な解決だけを求めるという体質が染みついてしまった。
たとえば、外交における戦略も「善か悪か」で判断するため、
善を探そうとするあまり、次の一手がどうしても遅くなる。
しかも、日本が「善かれ」と思って世界に主張したことは、
まずもって善として見られていない。
他国はリアリズムの視点で「日本が何を狙っているのか」
と冷酷に見ているのだ。
だからこそ、わが国も外交戦略を「善悪」ではなく、
「強弱」で見るように訓練しなければならない。
「強弱」とは、現在わが国にとって、
この政策は他国と比べて立場を強めてくれるのか
弱めるものかという冷静な判断である。
弱いのであれば、より強い政策を打ち出さなければならないし、
強いものであれば、政策をより国益に近づけなければならない。
こうしたリアリズムの思考を身につけることは、
むしろ「国際的なマナー」なのである。